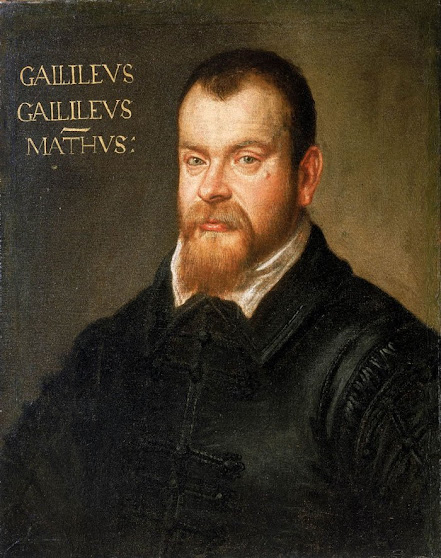前回までのところを纏めれば、以下のようになるだろう
知識や経験が真理と呼ばれるためには、その基礎に命令的、理想指示的な当為が仮定されている
当為という論理的良心の要求が基礎に立つことで真の認識になるのであり、模写説のように真なるものが客観的に実在するのではないことになる
これを模写説に対して、構成主義の真理観と呼ぶことにする
そこで問題になるのは、当為とは何なのかということである
当為とは、何かを真なる知識とするための基礎的予想で、それぞれの真理はそれぞれの当為を仮定している
各学問領域における真理は、その領域における当為を仮定している
普通、真理は仮定などのないものと思うだろう
そして、真理は唯一絶対であると主張したいだろう
著者はこれを、存在という太古からの謎を解かんとする我々形而上学的動物に共通する要求だと見ている
それはそれぞれの立場や仮定の上の諸真理ではなく、立場以前の真実在、世界や人生における真相を捉えようとする努力に繋がる
現象的実在から本質的実在に向かうのである
この無仮定として求める真理は偽に対立する真理ではなく、真偽以前の真理(真実在)、さらに言えば、絶対的真理とされるものではないかと著者は言う
それは真偽を超越したものであり、我々の要求に基づいた真理という意味で、我々が構成したものである
ここで、実在という概念について考えてみよう
絶対的真理として求められる真実在は、一切の立場から離れ、真偽の区別も超越するものである
真偽の別がないとすれば、それは真の実在とは言えないだろう
以前にも触れたが、我々とは独立に在るものは実在し、それが確かめられない幽霊のようなものは実在しないと言われる
ただ、その個人の心理においては実在していると言えないだろうか
それは、美なるもの、聖なるものについても当て嵌まるのではないか
このような考え方を絶対的真理にも適用できないだろうか
さらに、構成とは何を意味するのだろうか
著者は、実在を模写するという考え方を捨て、我々の主観が採用する立場によって構成されるのが実在であると考えている
真実在と言われるものは立場以前の主客未剖の世界であり、我々が普通実在と言うものは我々が経験し認識した何かで、真実在とは異なっている
我々は客観界をそのまま認識・経験するのではなく、何ものかを客観界として認識・経験するのである
ある立場に立っているから現れるものであり、当為の要求によって現れたものである
それが構成されるという意味であり、新たに創造されたものと言ってもよいだろう
ただ、この主張は個人的な要素が前面に出ていると受け止められ、独我論やジョージ・バークリーの唯現象論などと誤解される可能性もある
ここではそうではないとだけ言っておこう