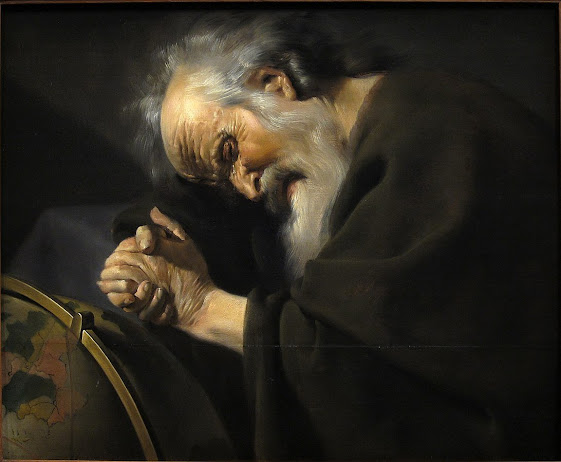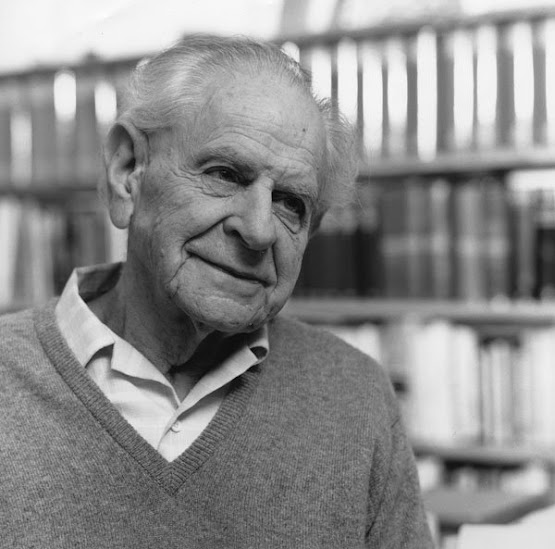2024年2月29日木曜日
ポパーによる「プラトンの呪縛」(13)自然と協定(3)
2024年2月28日水曜日
ポパーによる「プラトンの呪縛」(12)自然と協定(2)
素朴一元論から批判的二元論に発展していくが、その間にはいくつかの中間段階が発生する
その中で重要なものに以下の3つがある
1)生物学版自然主義
2)倫理的・法的実弟主義(Positivismus)
3)心理学的・精神版自然主義
興味深いのは、いずれも権力を擁護するためにも、弱者の権利を擁護するためにも使われたことである
1)生物学版自然主義は、法の下での人間の平等だけではなく、強者の支配という対立する主張を支えるためにも用いられた
最初の提唱者であるピンダロス(522/528-442/438 BC)は、強者には支配者になる使命があるという考えを擁護した
我々には同等の権利があることを強調した生物学版自然主義を最初に主張したのは、ソフィストのアンティポンであった
彼は、規範は恣意的であり、自然と対立するとし、規範は外部から押し付けられたものであるのに対し、自然法則は避けられないとした
エウリピデス(c. 480-c.406 BC)も、奴隷の名前以外はすべての点で自由な人間に比べて少しも劣らないと言い、ソフィストのアルキダマス(4th century BC)も、神はすべての人間に自由を贈った、自然は何人も奴隷とはしなかったと書いている
これに対してプラトン(427-347 BC)やアリストテレス(384-322 BC)は、ギリシア人と野蛮人は生まれつき不平等なのであり、生まれつきの主人と奴隷に対応すると考えていた
ある行動様式が自然であると認めることはできるので正当化も可能である
しかし、芸術、科学に対する関心や自然主義的論証への関心は自然なものではない
また、自然法則に即して生きるのがよいとされるため、健康の条件などを自然法則から導き出して生きることになる
しかし、自分の健康よりも高く評価していることがあることを見落としている
2024年2月26日月曜日
ポパーによる「プラトンの呪縛」(11)自然と協定(1)
2024年2月24日土曜日
Immunity: From Science to Philosophy は日本人として初めての試みか
2024年2月23日金曜日
ブログの1年が経過
2024年2月19日月曜日
ポパーによる「プラトンの呪縛」(10)静止と変化(4)
2024年2月18日日曜日
ポパーによる「プラトンの呪縛」(9)静止と変化(3)
プラトン(427-347 BC)が描いた完全国家、最善国家は具体的にどのようなものだったのだろうか
普通は、進歩主義者が抱くユートピアを目指すものではないかと解釈されてきた
しかしプラトンは、クレタやスパルタに見られる古代の原始社会の氏族的な形態を考えていたのではないかとポパー(1902-1994)は言う
この2つの都市国家は古いだけではなく、硬直して動きを奪われた石のようになっているが、これをさらに安定・強化しなければならないとした
そのために、内部分裂を免れ、階級闘争を回避し、経済的影響を最小にする方法を明らかにしようとしたのである
プラトンが考えたのは、平等に向かうのではなく、奴隷制国家、身分制国家であった
支配階級が打倒されることのない圧倒的力を持つことで、この問題を解決しようとした
支配階級だけが武器の携帯を許され、政治上の権利を持ち、教育を受ける権利を有したのである
プラトンの最善国家には、3つの階級がある
つまり、統治者、統治者のための武装した補助部隊戦士、労働者の3つだが、現実的には軍事に従事する支配者と被支配者の2つだけである
労働者は支配階級の物質的必要を満たすための家畜に過ぎないとプラトンは考えていた
金銭で売買された人間は奴隷として区別したが、その制度の廃絶についての言葉はないという
支配者階級だけが政治力を持つ状況下で問題になるのは、階級間ではなく支配者階級内での経済的利害の対立であった
そのために共産主義(私的所有の禁止、財産の共有、家族の解体、)が導入された
そこに、統一を脅かす富も貧困も存在してはならなかったのである
そして、支配者階級は被支配者階級に対して、人種、教育、価値判断という3つの点における優越性があると主張することで統一を正当化したのである
ポパーは、人間の優越性や卓越性がそのまま政治的権利の付与につながらないどころか、寧ろ道徳的責任が生じると考えている
2024年2月16日金曜日
ポパーによる「プラトンの呪縛」(8)静止と変化(2)
2024年2月15日木曜日
Immunity: From Science to Philosophy の紹介サイト
8月に刊行予定の拙著 Immunity: From Science to Philosophy の紹介が、もう Routledge のサイトに出ている
まだゲラの校正も始まっていない半年前である
日本の場合、ゲラの校正が終わりかける1~2か月前だったと記憶しているので、かなり早いという印象だ
また、この本を大学の授業で使う教師がいることを想定して、採用の判断の参考になる資料を用意しているとのことで、その申し込みも始めている
これも想定外のことであったが、向こうの出版社としては当然のことなのだろう
競争に晒されているからなのだろうが、外に積極的に働きかける姿勢が見える
開かれた感じがする
配送料は世界中どこでも無料とあった
2024年2月14日水曜日
ポパーによる「プラトンの呪縛」(7)静止と変化(1)
2024年2月12日月曜日
リマインダー: 春のカフェ/フォーラムのご案内
2024年2月11日日曜日
小澤征爾、そして東洋と西洋
小澤征爾氏が亡くなっていたことを知る
88年の人生だった
今の時代であれば、もう少し生きられたのではないかという気もする
ただ、病気との戦いだった後半生を考えると、その時が来たのかもしれない
その存在をいつ知ったのかは思い出せない
が、印象に残っているのは、学生時代に読んだ『ボクの音楽武者修行』(音楽之友社、1962年)だろうか
心躍ったことを思い出すと同時に、いつかは自分も外に出なければならないと思ったはずである
最初に実物に触れたのは、ボストンで研究生活を始めた1970年代後半のことになる
ボストン交響楽団の演奏会を聴くために行ったシンフォニーホールでのこと
颯爽と登場する姿を、どこか誇らしさを感じながら右側前方のバルコニーから見ていた
指揮者はオーケストラだけではなく、ホール全体を統御しているということを知った
残念ながら、当日のプログラムは思い出せない
それから7年に及ぶアメリカ生活だったので、何度もいろいろな媒体で触れていたはずである
その中で今でも印象に残っているのは、あるドキュメンタリー番組での彼の行動である
その時、チェリストのヨーヨー・マ(1955-)と屋外で対談(雑談)をしていたが、突然カメラの前に来てそれから先の撮影を遮ったのである
丁度、西洋音楽を東洋人が演奏することについての話題に入るところだった
当時はやや芝居がかっているなと思ったので、その深刻さには気づいていなかったのだろう
今回、テレビで流れていた映像を観ると、このテーマについて語っている場面も出ていた
あれから時間が経っているので客観度は増してはいるが、やはりそこに在る問題だということを認識できた
科学も同じように西洋由来のものであるが、音楽家ほどにはその壁を感じていないように見える
日本の近代科学は技術に集中することにより発展してきたからだろうか
しかしそのため、科学を支える精神的な文化に関する理解は乏しいというのが一般的な評価である
小澤によれば、若き日の日本は西欧の音楽に対抗するには技術しかないと考えていたようである
その点では科学と同じ出発点に立ったのだろう
遅きに失したとはいえ、今、それから先が求められる時代にいろいろな分野が入っているように見える
2024年2月8日木曜日
ポパーによる「プラトンの呪縛」(6)プラトンのイデア論
イデア論を理解するためには、ギリシアの神々と比較するとよく理解できるという
ギリシアの神々の一部は、部族の始祖の理想化である
こうした神々は完全であり、不死であり、永遠であるが、普通の人間は生成流転の中にある腐敗に晒されている
それがイデアとそれを模倣した知覚対象物との関係になる
銅版画や浮世絵のように、原版とそこから刷られた複製との関係と言ってもよいだろう
違いがあるとすれば、イデアの場合にはただ一つの形相しかないという唯一性である
似たようなものがあるとすれば、その形相を分有していると見るのである
これとヒストリシズムはどう関係するのだろうか
もし、流転するのがこの世界だとすると、それについて確定的なことは知り得ない
それにヒントを与えたのが、パルメニデス(c. 520-c. 450 BC)であった
パルメニデスは、経験から得られる見解とは別に、純粋に理性によって得られる認識は、不変の世界を持つことができると説いた
プラトン(427-347 BC)はこの考えに感銘を受けたが、それがは知覚対象物の世界と何の関係も持っていないことに不満を覚えた
彼はこの世界の秩序、政治的変動の探究に役立つ知識を得ようとしたのである
しかし、変遷する世界において確固として知識を得ることは不可能に見えた
そこでヒントを得たのが、ソクラテス(c. 470-399 BC)のやり方であった
ソクラテスが倫理について考える際に取った方法は、次のようなものであった
例えば1つの性質(賢明さ)について、さまざまな行動に現れる賢明さを論じ、そこに共通するものを明らかにする
アリストテレス(384-322)はこれを、その本質を取り出す作業と言っている
その本質とは、そのものに内在する力、あるいは変わらない内容を指している
アリストテレスによれば、ソクラテスは普遍的定義の問題を提起した最初の人ということになる
プラトンは、変化の中にある知覚対象物とは別に、その中にある普遍の本質的なものは知ることができるのではないかと考えた
それを形相あるいはイデアと名付けたのである
このやり方は、意識していたわけではないが、わたしが『免疫から哲学としての科学へ』の中で免疫の本質を探る際に用いたものと全く同じである
プラトンのイデア論は少なくとも3つの機能を持つという
1)この理論は、直接的には知り得ない変化する世界に対しても適応が可能になるので、社会や政治を分析する上で重要な補助手段となる
2)これは、変化の理論、腐敗の理論、すなわち生成と没落の理論への鍵を提供する
3)これは、ある種の社会工学への道を切り開き、政治的変化を阻止する道具を鍛えあげることを可能にし、腐敗することのない最善国家を示唆する
ポパーは、このようなプラトンの考え方を、方法論的本質主義(本質論)と呼ぶ
つまり、学問の課題は、隠されている本当の姿すなわち本質を発見し記述することにあるという考えである
その本性は、それらの始祖あるいは形相の内に発見されると考える
わたしの免疫論では、始祖とも言える細菌の免疫系にその本質が具現化されていたので、この点にも納得がいく
この考えと対極にあるのが、方法論的唯名論と名付けたものである
こちらは、対象の真なる本性を見い出し記述することは課題とはしない
その目的は、様々な状況下でどのように振る舞うのかを記述し、そこに規則性の有無を確認することである
例えば、エネルギーとは何かとか、運動とは何かという問いには意味を見出さない
そうではなく、そのエネルギーはどのように利用できるのか、惑星はどう動いているのかということが重要だと考えるのである
哲学者の中には、初めに定義が重要だと考える人もいるだろうが、実際の物理学はそれなしに問題なく動いている
つまり、この考え方は現代の自然科学が用いているものなのである
ただ、社会科学においては、未だに本質主義的な方法が採られている
ポパーは、それが社会科学の後進性を示していると見ているが、他の研究者は2つの領域は本質的に違うという判断を下しているという